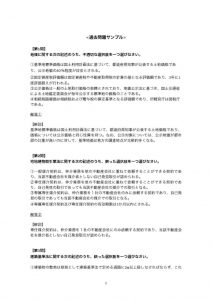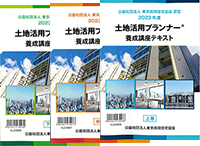提案の幅が広がる!!
「土地活用の専門資格」で地主の信頼を獲得!提案の幅が広がる!!「土地活用の専門資格」で地主の信頼を獲得!
CBT試験:
2026年2月7日(土)~2026年2月24日(火)
CBT試験申込受付期間:
2025年11月4日(火)~2026年2月21日(土)
全国にあるお近くの試験会場で受験できます!会場の一覧はこちら!
CBT試験お申込受付終了[2月21日(土)]まであと・・・
土地活用の専門資格「土地活用プランナー」とは?
内閣府から公益認定を受けている公益社団法人東京共同住宅協会が運営する「土地活用の専門資格」。
土地活用提案に必要な実務知識を体系的に学び、営業提案に即活かせる資格です。
土地活用の専門家であることを、「資格」という形で証明できる強みがあり、土地オーナー様と関わる機会の多い不動産業界、建築業界の方々を中心に受験されています。【サンプル問題プレゼント!!】無料オンラインガイダンス動画配信中
土地活用プランナー無料オンラインガイダンス動画をYouTubeにて配信いたしました。
ご視聴の特典として、サンプル問題をプレゼントしております。
ご視聴を希望される方は、下記の手順でお申し込みください。【お申し込み方法】
(1)こちらのフォームに必要事項を入力
(2)申し込み直後に送信される自動返信メール記載の動画のURLをクリック
※特典サンプル問題のダウンロードURLも記載しております【ガイダンス内容】
・土地活用プランナーとはどのような資格か?
・土地活用プランナーで学べる知識・スキル
・試験に合格するための効率的な学習方法
・資格取得後のメリット
など、資格の概要から取得後の活かし方について解説いたします。資格の必要性とメリット -なぜ、今この資格が必要なのか?
土地活用の専門性と根拠を求められる時代に
複数の業者が競って提案する時代。
提案に「納得感」がなければ、すぐに他社に流れてしまいます。・根拠のある収支シミュレーション
・エリア特性を踏まえた活用アイデア
・税制・補助金・法令にも配慮した提案これらができてこそ、地主に「この人に任せよう」と思わせることができるのです。
「説得力のある提案」ができるかどうかが、受注を左右します。
そのための実践力を身につけられるのが「土地活用プランナー」です。■営業成績UPにつながる ■地主からの信頼獲得
■他社と差がつく武器に ■資格名で提案に説得力CBT試験概要
試験期間 次回試験実施期間:
2026年2月7日(土)~2026年2月24日(火)試験申込受付期間:
2025年11月4日(火)~2026年2月21日(土)試験会場 全国300ヵ所以上のテストセンター
詳しくはこちらをご参照ください。学習時間 20~30時間程度 合格基準点 24点(40点満点、正答率60%) 試験形式 CBT四肢択一式 試験時間 60分 受験料 8,800円(税込)
全国にあるお近くの試験会場で受験できます!会場の一覧はこちら!合格への近道
土地活用プランナー公式テキスト
法務、税務、資金計画、事業収支計画、建物完成後の賃貸管理や建物管理まで、土地活用の全てを網羅した公式テキスト 6,600円(税込)
※「過去問サンプル」「テキストサンプル」は、画像をクリックすると拡大されます。
通信講座
無理なく学べる!LEC東京リーガルマインドで試験対策講座(WEBまたはDVD)を販売中
・試験出題頻度の高い項目を中心に重点的に解説!
・通信講座受講生の合格率は90%以上![受講料]
WEB講座 ⇒ 27,000円(税込) DVD講座 ⇒ 29,000円(税込)
~試験直前期に実施するポイント解説講座のオプション付き!~
よくある質問
CBT試験について教えてください。
CBTとはコンピュータを使った試験方式のことです。指定された期間の中で任意の日時に、全国300か所以上あるテストセンターで受験することができます。
※CBT試験の流れについてはこちらを参照
どんな人が受験していますか?
不動産業界、建設業界にお勤めの方を中心に受験されており、受験者全体の7割以上を占めています。
合格率はどれくらいですか?
合格率は約75%です。40点満点中24点で合格となります。
登録のメリットについて教えてください。
登録者の方には認定カードが発行されます。「土地活用プランナー」の名称を使用でき、地主に対して土地活用のプロであることをアピールできます。また、年4回の会報紙、フォローアップセミナーなどの特典があります。